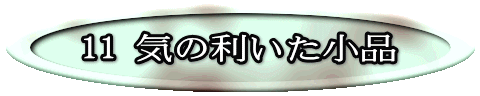
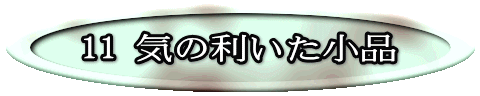
…とタイトルを決めてみたものの
その名に恥じないものが書けるか。
書けまい。
しかし、願望としては、そうありたい。
| 身体その1 2012.7.11 |
腑に落ちる 人の話がよく解ること。納得できるときに用いる。 それが、なぜ「腑」に「落ちる」のか。第一、「何が」落ちるのか。 気が肚(はら)に落ちる、であろう。 では、気はそれまでどこにいたのか。身体の上のほうをうろついていたのであろう。たいていは後頭部のあたりか。気が身体の上辺でうろつく感じは「気が騒ぐ」「気が乱れる」「気が落ち着かない」「気が気でない」などと言い、胸のあたりでつかえると「気が滅入る」などと表現する。 日本人はよほど体内の気の感覚に敏感である。気の本場は中国かもしれないが、中国人にはそういうデリカシーはない。もっとも、今の日本人の気の感覚もすっかり衰えてしまって「気の言語表現」もこうして解説してもらってようやく(そうだったのか)と理解される社会となりはてた。 気は腹に据わっているものである。 …という前に、腹と肚と腑についてまとめておこう。 腹はいわゆる「おなか」で、胴体の前の側の胸の下の骨のないエリア。臍を中心にした丸い部分。そのうち臍を含む下方の直径一尺の円で切り取れる部分を「小腹」(しょうふく)と呼んでいる。俗にいう「臍下丹田」の別名である。 肚は象形文字ではなく観念文字で、五行思想が円熟して以降の創作文字である。五行とは宇宙を構成する五素「木火土金水」が互いに関係を結んだり解いたりしながら運動することをいうのだが、土を中心に木火金水が周りを囲むとする考え方があった。土は大地で、土台であり、中心に位置するものと意味づけされた。身体の中心はどこか。古人は迷うことなく、おなかだと感じた。それで、肉体を意味する月を左側にへんとして置き、右側に意味を表わす土をつくりにして組み合わせて「肚」としたのだ。だからお腹が減ったと書き、腹をかかえて笑うと書くが、腹が決まると書くと、ちょっとちがう感じがする。ここは肚が決まると書きたい。抽象的な表現には肚が適している。しかし、腹はあくまでも腹だ。腹には臓物が詰まっている。 腹に詰まっている臓物を、「腑」という。腑という文字は月+府である。府は政庁のことで、昔は首都のことを首府ということが多かった。戦前は東京府大阪府京都府といって、都城のあったところを地方のニュアンスのある県とは別に府とした。奈良が府でないのはなぜか…これも面白い話だが、ここはさておこう。腑はすなわち肉体の中心という意味になる。中心を貫くのは、消化管である。実際にはぐにゃぐにゃ曲がっていて進化の過程で長くなりすぎて折り畳んだり膨らんだり窄めたりした結果だが、中心は中心で、胃の腑という言い方がまだある。中国古典医学では小腸も大腸も腑である。一般に臓物のうち袋と管は腑と言われる。それはそれだ。原義は腹と同じである。 そこで再び、何が腑に落ちるのか、考えてみよう。 気が落ちるのだけれど、何の気が落ちるのか。 それは「人の話の気」が自分の腹の「腑」に落ちる、落ち着く、ということであろう。 なぜ、腑に落ちるのか。それは、腹に心があるからである。赤心という言葉がある。腹を割って話すという言い方がある。切腹だって、腹に誠があることを証明するためにやったのだ。腑に落ちるという言い方にもっとせ近い表現は「得心がいく」ではないか。 気功では、心まで形をとる以前の「気」のままで扱い、気が腹に落ちることを「気沈丹田」という。■ |
| 全インデックスにもどる | ブロックメニューBにもどる | 隣のページ13にすすむ← | 隣のページ10にすすむ |